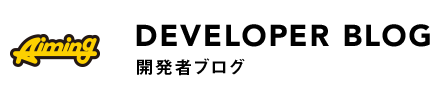第2事業部 企画部って何するの? ~『カゲマス』の「タッグキャラ」開発事例で見る、チームの仕事術~

はじめに
こんにちは。
本日は、第2事業部TeamCaravanの企画部の仕事内容と、日々どのような専門チームと連携して一つのコンテンツを作り上げているのかを、具体的に紹介いたします。
題材として、『陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン』(カゲマス)の1.5周年の目玉として実装された「タッグキャラ」を取り上げます。
この機能が、どのようなチームの力が合わさってお客様の元に届けられたのか、その裏側を主に仕様/実装/調整を担当したプランナーの田橋と演出を担当したプランナーの片桐でお送りいたします。
第1章:要件定義と提案書の作成
新規開発を行う際は、まずプロジェクトで目標を定め、それを実現するための「要件」を決めます。でもプランナーの仕事は、それをそのまま形にすることではありません。
まず最初に、要件やシステムという制限の中で、いかにお客様を楽しませられるかを考えていきます。
バトル班側の要件定義:
「タッグキャラを表現したい。しかし、2キャラが同時に同じ画面で戦ってしまうと、端末負荷の問題で表示ができない」
どうやってタッグキャラを実装するか
どのようにすれば1体でもタッグ感を出せるかをチームメンバーに相談しながら考えていきました。
その結果、バトルの一番の目玉である奥義でタッグ演出を行い、その後バトンタッチのような形でキャラクターが交代するという演出に行き着きました。
この仕組みであれば、1回のバトルで2体を使える嬉しさに加え、「キャラBで敵にデバフをかけて攻撃や防御力を下げ、キャラAに交代して味方をバフし、PT全体の火力を上げる」など、タッグならではの戦略的な戦い方ができると考えたのです。
方向性が決まったら、みんなが共通イメージを持てるよう提案書を作成し、ディレクターと運営さんを集め会議を開きます。
ここでは、注意すべき点や不安要素についてのFBをもらったり、課題に対して一緒に考え、みんなで仕様を作り上げていきます。
演出班側の要件定義:
「カッコよさ」という抽象的な概念を、どう「共通言語」に翻訳するか一方、演出班に与えられた要件は「2人のキャラをいかにカッコよく表現するか」という、より抽象的なものでした。
「カッコいい」の定義は人それぞれです。例えば、ここを定義しないと各セクションのクリエイターが、それぞれの「カッコいい」を制作してしまい、結果として、個々のクオリティが高くとも、全体的な一貫性がないものになってしまいます。
そこで私たちがまず定義したのが、「普段の関係性よりも、一歩進んで息ぴったりなライバル感」という、より具体的な、誰にでも伝わる定義でした。この「ライバル感」という“定義”を軸にすることで、初めてチーム全体で具体的なディスカッションが可能になります。
そこから例えば、「登場演出は、あえて背中合わせにすることで、互いへの信頼を表現してはどうか」「戦闘中は息ぴったりなのだから、戦闘後の勝利演出では2人がいつも通りに張り合うのはどうか」などといったように、判断基準ができあがるのです。

第2章:仕様書作成
こうして練り上げたコンセプトやアイデアを、開発チームの誰もが理解できる具体的な「仕様書」という設計図に落とし込むのも、プランナーの重要な仕事です。
バトル班、演出班、そしてUIなどを担当する機能班が連携し、一つの大きな仕様書を完成させます。
仕様書が完成すると、私たちはこれを手に、プロジェクトの「ハブ」として各分野の専門家たちと連携し、開発を推進します。
プランナーが考えたコンセプトや仕様を、UIデザイナーさんが画面デザインを作成し、各種エンジニアさんがプログラムを組み、そしてイラストさんやモーションさん、サウンドさんといった多くのクリエイターが関わります。
その他にも、シナリオさん、運営さん、進行管理さん、デバッグさんなど、様々なチームと連携しながら、一つのコンテンツが作られていきます。
仕様書の「裏側」を伝えるコミュニケーション
仕様書は機能の「設計図」ですが、それだけでは最高のモノづくりは生まれません。私たちプランナーが同じくらい大切にしているのが、仕様書を介したチームとのコミュニケーションです。
仕様書に記された一行の裏側にある「なぜ、そうするのか?」という意図や想いをチーム全員で共有することで、各分野の人たちから「それなら、良い方法がありますよ」といった、私たちの想像を超えるアイデアが生まれる場合があるからです。
具体例①:UIデザインとの連携
バトル班が作成したタッグの仕様書には、「バトル中のキャラアイコンは専用アイコンを設定する」と記載がありました。
その背景にあったのは、単なる識別のためのアイコンではなく、「タッグキャラは特別な存在なのだ、という所有感をバトル中もお客様に感じてほしい」という私たちの強い想いです。
この想いを共有したところ、UIデザイナーさんは、限られた表示領域の中でも「特別感」と「視認性」を両立させる、素晴らしいアイコン案を複数提案してくれました。
具体例②:演出クリエイターとの連携
演出側では、バトルの各種演出を盛り込んだ「スキル発注指示書」を作成します。
ここでは、主にテキストと画像や動画などのイメージを使いながら発注指示書に落とし込んでいきます。
それを元にディレクターやアートさんの作業者にフィードバックをもらいます。
そして、この発注段階でも大切にしているのが、「なぜ、この演出をしたいのか/この演出になるのか」という理由を添えることです。
例えば、「○○という完成図を目指しているので、△△という演出になってほしい」というこちらのやりたい理由がしっかりと伝われば、「そうであれば、△△よりも□□の方が良いと思いますよ」などと適切に相手が打ち返してくれます。
プランナーは決してその道の専門家ではありません。ただ、企画段階から全体を知っているのはプランナーです。なので、発注指示書にはプランナーのやりたいことを込めるようにしています。
このように相談をして進めた結果、下記の素晴らしい奥義演出ができました。

仕様書、発注指示書は、一方的に仕事を依頼するものではなく、チームでゴールを目指すためのコミュニケーションツールです。
だからこそ、私たちはその一つ一つに、お客様に届けたい「想い」や「体験」を、熱意をもって込めるようにしています。
第3章:バトルバランス調整
キャラクターの演出やタッグ機能が形になったら、次はその「面白さ」を創り込むフェーズに入ります。
どんなにキャラクターの演出が格好良くても、その性能が伴わなければ、お客様に本当の魅力を届けることはできません。
見た目の期待感と、実際に使った時の強さや楽しさが一致して初めて、キャラクターはその真価を発揮します。
キャラをより魅力的にするか殺してしまうかはバトル班の一番の腕の見せ所です。
まず、私たち企画(バトル班)は、運営さんやディレクターと連携し、今回のタッグキャラのコンセプトを固めました。
- イプシロンは、味方の火力を引き上げる「バッファー」
- ベータは、敵を妨害し味方の生存率を上げる「デバッファー」
このように、明確な役割分担を持たせることにしました。
しかし、ここからがバランス調整の難しいところです。
例えば、どちらか一方の性能が強すぎると、そちらのキャラクターばかりが使われ、編成に偏りが生まれてしまいます。それでは、せっかくの「タッグ」ならではの良さが活かせません。「どこまで味方を強化すれば、強すぎないか」「どこまで敵を弱体化させれば、ゲームが壊れないか」。この絶妙なバランスを、調整していかなければなりません。
検証中は、外部のバランス検証専門チームも交えたテストプレイを何度も繰り返しながら日々議論を重ねていきました。
その結果、お客様が挑むコンテンツや成長度合いに応じて、「ここはイプシロンの火力支援だ」「この強敵相手には、ベータの妨害で耐えよう」と、戦略的にスイッチする楽しさを生み出すことができたのです。
タッグだからこそできる、奥深い戦略性を秘めた、絶妙なバランスのキャラクターを完成させることが出来ました。
第4章:デバッグ検証
面白さのバランスが決まると、いよいよ品質の確認をします。
まず、IP(原作)の世界観やキャラクターのイメージを損なっていないかを、関係者の方々に確認していただく「監修」を行います。
プランナーは、意図が正確に伝わるように、補足資料などを準備してこの監修に臨みます。
そして、品質を守る最後の砦が「デバッグ(品質チェック)」です。ここでは、デバッグさんと連携し、あらゆる観点から不具合(バグ)がないかを徹底的に検証します。
もし問題が見つかれば、すぐさまエンジニアさんやデザイナーさんと解決策を協議します。時には進行管理さんとスケジュールの再調整を行うこともあります。
第5章:お知らせとヘルプ作成
品質の目処が立つと、今度はお客様に新機能の魅力を伝える準備が始まります。
私たちプランナーから、お知らせ・ヘルプ作成を運営さんに依頼します。共有する際は今回のタッグキャラの魅力や、仕様で特に注意してほしいポイントなどを伝えます。この情報をもとに、運営さんの担当者が、お客様の期待感を高める「お知らせ」や、機能について分かりやすく解説する「ヘルプ」を作成します。
プランナーの想いを、お客様に届く「言葉」に変換してもらう、非常に大切な連携です。

最後に
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
プランナーの仕事の、リアルな思考プロセスの一端が伝わりましたでしょうか。
与えられた条件の中で、いかにお客様に最高の体験を届けるかを考え抜き、多くの仲間たちの力を借りて、それを形にしていく。
大変なことも多いですが、これこそがプランナーという仕事の醍醐味です。
私たちの職場は、チームで何かを創り上げ、誰かの「楽しい」のために全力を尽くすことに喜びを感じる方にとって、最高の場所です。
もしご興味を持っていただけたら、ぜひ採用ページもご覧ください。
-
前の記事

技術書典18に参加しました(^ ^)/ 2025.07.15
-
次の記事

MySQLとTiDBの一貫性読み取りの違い 2025.08.26